SNS時代の育児で感じる『比較』のプレッシャー
インスタグラムやツイッターなど、SNSが生活の一部となった現代。育児をする中で、他の家庭や子どもの成長記録がタイムラインに流れてくる光景は、日本の新米パパ・ママにとって日常茶飯事になっています。「あのおうちの赤ちゃんはもう歩き始めた」「同じ月齢なのに、うちの子はまだ言葉が出ていない」――ついつい他人と自分を比べてしまう気持ちは、多くの親御さんが感じていることではないでしょうか。特に日本社会は「みんなと同じであること」に安心感を覚える傾向が強く、周囲との差異に敏感になりがちです。そのため、SNS上で目にする華やかな育児投稿や、順調な成長記録を見るたびに、自分の育児に自信を失ったり、不安を抱えたりすることも少なくありません。このような「比べてしまう」心理は決して珍しいものではなく、むしろ多くの家庭が直面する共通の悩みです。本記事では、そんなSNS時代ならではの育児環境と、「比べてしまう自分」とどう向き合うかについて、新米パパ目線で掘り下げていきます。
2. 他人と比較してしまう自分を責めないコツ
パパになってから、SNSで他の家庭や子どもたちの成長を見て「うちの子はどうなんだろう」「自分はちゃんとできているかな」とつい比べてしまうこと、正直ありますよね。僕自身も、インスタグラムやツイッターで同年代の子がもう歩き始めたり、おしゃれな離乳食を作っていたりする投稿を見ると、焦ったり落ち込んだりすることがありました。でも、そんな自分を責める必要はありません。「比べてしまっても大丈夫」という気持ちになれる、簡単なマインドセットを紹介します。
「比べる」ことは自然な感情
まず知っておきたいのは、「他人と比べる」のは人間のごく自然な反応だということです。特に日本社会では「みんなと同じであること」が良しとされがちなので、無意識に周囲と比較してしまうのは仕方ありません。自分だけじゃない、と自覚することで、少し心が軽くなるはずです。
比べてしまった後の心の持ち方
もしSNSで誰かの投稿を見て「うらやましい」と感じたら、その気持ちを否定せず、一度受け入れてみましょう。そして下のように、自分への声かけを変えてみるのがおすすめです。
| よくある心の声 | パパ的・前向きセルフトーク |
|---|---|
| 「うちの子、遅れてる?」 | 「成長には個人差があるから大丈夫」 |
| 「自分はダメなお父さんかも…」 | 「完璧じゃなくても、一生懸命やってる自分を認めよう」 |
| 「あんな風にできない…」 | 「うちにはうちのペースがある」 |
心に寄り添う小さな習慣
・毎日一つ、自分ができたことや楽しかったことを書き出す
・SNSを見る時間を決めて、疲れたらスマホから離れる
・家族やパートナーに悩みを話してみる(話すだけでもスッキリ!)
こうした習慣を取り入れることで、「比べてしまう自分」を否定せず、ゆるやかに受け入れられるようになります。パパとしても一人の人間としても、無理せずマイペースで大丈夫ですよ。
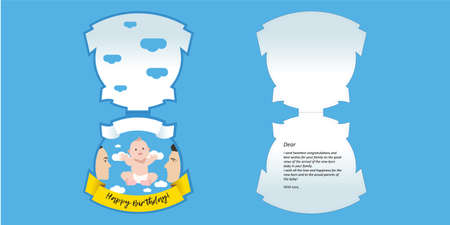
3. 日本ならではの子育て観と期待にどう向き合うか
SNSで他の家庭の育児風景が簡単に見える時代、つい「うちの子は大丈夫かな?」と比べてしまう自分がいます。でも、日本の子育てには、独特の価値観や地域とのつながりがあります。
たとえば、祖父母からの「昔はこうだった」というアドバイスや、地域コミュニティの目、保育園の先生方からの日々のフィードバック。これらは、ときにプレッシャーになることもありますが、同時に頼れる存在でもあります。
祖父母との関係性を活かす
祖父母世代は経験豊富ですが、今とは時代背景も違います。昔ながらのしつけや考え方をそのまま受け入れる必要はありません。「そういう時代もあったんだな」と一度受け止め、自分たち家族に合った方法を選びましょう。また、サポートしてもらえる部分には感謝し、「ありがとう」と伝えることで、お互い気持ちよく子育てに関われます。
地域コミュニティとの距離感
日本ではご近所づきあいや町内会など、地域との関わりが大切にされます。他人と比べる要因にもなりますが、「困ったときはお互い様」という意識が根付いているのも事実。無理に合わせようとせず、自分たちにできる範囲で交流すれば十分です。イベント参加や挨拶など、小さな関わりでも自信につながります。
保育園・幼稚園の先生との連携
保育士さんや先生方から「〇〇ちゃんはこんなことができましたよ」と報告を受けると、他の子との差を感じてしまうことも。でも、それぞれ個性やペースが違うもの。積極的に相談したり、不安な点は正直に伝えたりすることで、一緒に成長を見守ってくれる存在になります。
日本文化ならではの期待とうまく付き合うコツ
他人と比べたくなる気持ちは自然なもの。大切なのは「誰かと同じ」でなく、「自分たちらしい」子育てを選ぶこと。周囲からの期待やアドバイスは参考程度にしつつ、自分と家族の価値観を大事にすることで、SNS時代でもブレない心を育てられます。
4. 日々の『できた』を見つける習慣づくり
SNSで他人と比べる代わりに、自分の成長に目を向けよう
SNSでは、どうしても他の家庭のキラキラした育児シーンが目についてしまいがちです。「○○ちゃんはもう歩いた」「△△くんはこんなに話せる」など、比べることで不安や焦りが生まれることも。しかし、育児は子ども一人ひとり、そして親自身のペースで進むもの。他と比べるのではなく、日々の小さな『できた』を見つけて、お子さんや自分自身の成長をお祝いする習慣を持つことで、前向きな気持ちになれます。
『できた』記録アイディア集
日常生活の中で「今日できたこと」を見つけて記録する方法はいろいろあります。おすすめの方法を下表にまとめました。
| アイディア | ポイント |
|---|---|
| 育児ノートに手書きで記録 | シンプルで続けやすい。寝る前のリラックスタイムに◎。 |
| 家族LINEやグループチャットで報告し合う | パパや祖父母とも共有できて、みんなで成長を喜べる。 |
| カレンダーにシールを貼る | 子どもと一緒に楽しめて視覚的にも分かりやすい。 |
| フォトアルバムアプリで写真と一言コメント | 後から見返す楽しみが増える。忙しい時でも簡単。 |
小さな成長こそ大切に
「今日は自分で靴下を履けた」「離乳食を全部食べられた」「朝から怒らず過ごせた」など、どんな些細なことでもOK。それぞれの家庭、その日のコンディションによって“できた”は違います。だからこそ、小さな達成感や喜びを意識して残していくことが大切です。
新米パパからひと言
私自身も、SNSで他のお子さんを見ると「うちの子は大丈夫かな?」と不安になることがあります。でも、「昨日より少しだけ早く起きられた」とか、「今日は絵本を1冊多く読めた」など、本当に小さな変化を記録することで、自分も子どもも着実に成長していることを実感できます。毎日の『できた』探しが習慣になると、自然と自信が湧いてきますよ。
まとめ
SNS時代だからこそ、周囲との比較より、自分だけの“できたストーリー”を書き溜めていきましょう。それが心の余裕につながり、家族全体の笑顔にもつながります。
5. SNSの上手な付き合い方、情報との距離の作り方
現役パパが実践するSNSとの向き合い方
SNS時代の育児は、便利さと同時に「情報疲れ」や「比較ストレス」をもたらすこともあります。新米パパとして私自身も、他の家庭の育児投稿を見て「うちは大丈夫かな…」と不安になることがよくありました。そこで意識的に心がけているSNSとの付き合い方をご紹介します。
情報を取り入れる「時間」と「頻度」を決める
育児情報や他の家族の様子が気になるものですが、何度もチェックすると疲れてしまいます。私は朝と夜だけSNSを見るようにし、通知もオフにしています。「今は子どもと遊ぶ時間」と決めて、スマホをリビングに置きっぱなしにする工夫もしています。
自分なりのフィルターを持つ
SNSにはキラキラした投稿が多いですが、「全て真実じゃない」「それぞれのペースがある」と自分に言い聞かせるようにしています。また、本当に信頼できる育児アカウントだけフォローすることで、情報過多にならないようコントロールしています。
オフラインの時間を大切にする
週末は家族で公園に行ったり、友人家族と会うなどリアルな交流を増やしています。ネットでは得られない安心感や共感を感じることができ、SNSへの依存度も自然と下がりました。
ちょっとした工夫で心も軽くなる
SNSを完全にやめる必要はありませんが、「自分や家族のペース」を守るためには距離感を大切にすることがポイントです。小さな工夫で心が軽くなり、子どもとの時間にも余裕が生まれるはずです。
6. 夫婦でできるメンタルサポートのアイディア
お互いを励まし合う大切さ
SNS時代の育児では、どうしても他の家庭や親子と自分たちを比べてしまいがちです。そんな時、一番身近なパートナーである夫婦がお互いに「よく頑張っているね」と声をかけ合うことは、とても大きな支えになります。たとえば、「今日もお疲れさま」「○○ちゃんのお世話、本当に助かったよ」と小さな感謝や労いの言葉を意識的に伝え合うことで、お互いの自信や安心感につながります。
思いを共有する時間をつくろう
日々の忙しさで会話が減りがちですが、夜寝る前や子どもが寝静まった後など、ほんの数分でも「今日はこんなことで悩んだ」「SNSでこういう投稿を見て、ちょっと落ち込んだ」など、自分の思いや感じたことを素直に共有する時間を作ることが大切です。相手の話を否定せず、まずは「うん、そうなんだね」と受け止める姿勢が、安心して本音を話せる雰囲気につながります。
二人だけのルールや合言葉を決めよう
例えば「SNSは参考程度」「私たちは私たちらしく」など、夫婦で前向きになれる合言葉やルールを決めておくと、比べすぎてしまった時にも心のブレーキになります。二人だけの小さな約束ごとは、不安になった時のお守りになります。
一緒に深呼吸・ストレッチタイム
育児中はどうしても緊張やストレスが溜まりがちです。そんな時は、夫婦で一緒に深呼吸や軽いストレッチをするだけでもリラックス効果があります。「今日も1日お疲れさま」と声をかけながら体をほぐすことで、お互い心も体もリセットできます。
まとめ:夫婦で支え合うからこそ乗り越えられる
SNS時代ならではの不安や比較による悩みも、夫婦で支え合うことで少しずつ和らげることができます。「一人じゃない」という実感が、育児のメンタル面において何よりも強い味方になります。無理せず、できることから夫婦で始めてみてください。

