わが家のおうちモンテッソーリを始めたきっかけ
私がモンテッソーリ教育に興味を持ち始めたのは、子どもが自分でお片付けをしたり、身の回りのことに挑戦する姿を見て、「もっと自主性や自己肯定感を育ててあげたい」と感じたことがきっかけでした。日本の育児本やSNSでも「おうちモンテ」といった言葉をよく目にするようになり、日常生活の中でできる小さな工夫から始めてみようと思いました。
最初の一歩は、子どもが自分で手に取れる高さにおもちゃや絵本を並べることでした。リビングの一角に専用スペースを作り、「自分で選ぶ」「自分で戻す」という流れを意識してみました。日本の家庭ではスペースの制約もありますが、無理なくできる範囲からチャレンジすることで、親子ともに新鮮な発見がありました。
この体験を通じて、「やらせる」のではなく「見守る」ことの大切さにも気づきました。忙しい毎日の中でも、一緒に過ごす時間や声かけを少し変えるだけで、子どもの表情や行動が変わっていく様子を実感しています。
2. 手軽にはじめる!日本の家庭でできるモンテッソーリ活動例
モンテッソーリ教育と聞くと、特別な教材や大きなスペースが必要だと思われがちですが、日本の一般的なご家庭でも、身近なアイテムや日常生活の中で無理なく取り入れることができます。ここでは、日本のご家庭ならではの工夫や、お子さんと一緒に楽しめる実践例をご紹介します。
家事手伝いを通して「できる」を増やす
日々の家事は、まさにモンテッソーリ活動の宝庫です。お米を研ぐ、洗濯物をたたむ、食器を並べるなど、お子さんも自分でできそうなことからスタートしましょう。失敗も成長の一部なので、「一緒にやってみよう」という気持ちで見守ることがポイントです。
| 家事内容 | 年齢の目安 | 親の声かけ例 |
|---|---|---|
| 野菜を洗う・ちぎる | 2〜3歳 | 「これを一緒に洗ってみよう」 |
| 洗濯物をたたむ | 3〜4歳 | 「タオルを半分に折ってくれる?」 |
| テーブルセッティング | 4〜6歳 | 「お皿を運んでお願いね」 |
日用品を使ったアイデアで「自主性」を育てる
例えば、子どもの手が届く場所にコップやタオルなどをセットしてあげるだけで、「自分でやりたい!」という気持ちを応援できます。また、100円ショップには、小さなトングやミニサイズのお掃除グッズなど、子どもにも扱いやすい商品がたくさんあります。こうしたアイテムを活用することで、家庭内でのお手伝いもぐっと楽しくなります。
100円ショップで揃う!おすすめアイテム一覧
| アイテム名 | 活用シーン | 特徴・メリット |
|---|---|---|
| 小さいトング | お弁当作り、お菓子掴み遊び | 指先トレーニングにも◎ 衛生的に使える |
| ミニバケツ&ぞうきん | お掃除ごっこ、水遊び | 本物そっくりで達成感UP!片付け習慣にも役立つ |
| 仕切り付き小物ケース | ビーズ遊び、小物整理整頓練習 | 分類・順序づけ力が育つ 色んな用途に対応可 |
親子で楽しむためのポイントは?
最初は「完璧」を求めず、「できた!」という小さな達成感を大切にしてください。また、日本独自の生活習慣(靴箱に靴を並べる、玄関掃除など)もモンテッソーリ的視点で見ると素敵な学びになります。親子で声かけしながら、日常生活そのものを豊かな体験に変えていきましょう。
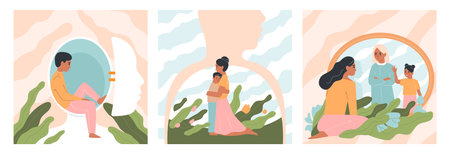
3. 子どもの反応と成長の変化
おうちでモンテッソーリ教育を取り入れ始めてから、子どもたちの行動や気持ちにさまざまな変化が見られるようになりました。最初は「自分でできるかな?」と不安そうな表情を浮かべていた子どもも、日々の活動を重ねるごとに自信を持って取り組む姿が増えていきました。
小さな「できた!」の積み重ね
例えば、朝のおしたくボードで自分で服を選んだり、お箸を使って豆を移し替える作業など、モンテッソーリ活動には「自分でやってみる」チャンスがたくさんあります。「できたよ!」と嬉しそうに報告してくれる瞬間は、親としても胸がじんわり温かくなるものです。失敗しても「もう一回やってみる」と前向きな気持ちになる様子から、挑戦することの楽しさを実感しているようでした。
自立心と自己肯定感の芽生え
毎日の活動を通して、少しずつですが手伝いなしでも自分のことができるようになったり、「ありがとう」「ごめんなさい」などの言葉を自然に使えるようになりました。家庭内でも「お手伝いしたい!」と積極的に声をかけてくれるようになり、小さな責任感や達成感が芽生えていることが感じられます。
印象的だったエピソード
ある日、おやつの時間に自分で果物を切ってお皿に盛り付けるという活動をした時のことです。初めは包丁を持つ手が震えていましたが、「ゆっくりね」と声掛けすると、一生懸命集中して切っていました。出来上がったお皿を家族に「どうぞ」と差し出す姿は、とても誇らしげで、「自分にもできる!」という自信が満ちあふれていました。このような経験から、子ども自身だけでなく親としても、子どもの可能性に改めて気づかされました。
4. 親としての気づきと成長
おうちモンテッソーリを実践する中で、親として多くの気づきと成長がありました。最初は「子どもに何を教えればいいのか」「正しくできているのか」と不安でしたが、日々の関わりの中で少しずつ考え方や接し方が変化していきました。
子どもの自主性を信じることの大切さ
モンテッソーリ教育では、「子どもは自分でできる力を持っている」という考え方が根本にあります。以前は、つい先回りして手助けしたり、危ないからと止めたりすることが多かった私ですが、活動を通して「見守る」ことの大切さを学びました。子どもが自分なりに考え、挑戦し、失敗してもまたやり直す姿を見ることで、「待つ」ことができるようになりました。
親自身の変化と学び
| 以前の私 | おうちモンテッソーリ後の私 |
|---|---|
| すぐに口出し・手出しをしていた | まずは見守り、子どもの意志を尊重するようになった |
| 失敗を避けさせていた | 失敗も経験の一部と受け止められるようになった |
| 「できた・できない」で評価していた | 過程や努力を認める声かけに変化した |
関わり方の具体的な変化
例えば、朝のお支度で靴下を履く時も「自分でやってみたい」という気持ちを尊重し、時間がかかっても見守るようになりました。また、お片付けや食事のお手伝いでも、「ありがとう」と感謝を伝えることで子どもの自己肯定感が高まることにも気づきました。
親として成長する喜び
おうちモンテッソーリは、子どもの成長だけでなく親自身にも多くの学びと気づきを与えてくれます。日々の小さな成功体験や発見を通じて、親子ともに成長できる時間となっています。
5. 日本でモンテッソーリを続ける上での工夫と悩み
日本ならではの環境と文化的な課題
日本でおうちモンテッソーリを実践する中で、最も感じたのは住環境や近隣との関係です。多くの家庭がマンションやアパートに住んでいるため、大きな音や動きには注意が必要です。子どもが自由に活動できるスペースを作ろうと思っても、家具の配置や収納場所など、日本の住宅事情ならではの工夫が求められました。また、日本の文化として「周囲に迷惑をかけないこと」を大切にしているので、子どもの自主性を尊重しつつも、どうしても「静かにしてね」と声をかけてしまう場面が多いです。
周囲の目と親自身の気持ち
公園や児童館などで他のお母さんと話すと、「どうしてそんなに子ども任せなの?」と不思議そうな顔をされることもありました。日本では「みんな一緒」「ルールを守る」ことが重視されるため、モンテッソーリ流の“見守り”スタイルは時に浮いてしまうことも。私自身も最初は不安でしたが、少しずつ自信を持って説明できるようになりました。親として「この選択でいいのかな?」と悩む日々ですが、子どもの変化を見るたびに続けてよかったと感じています。
教材・おもちゃ選びのリアルな工夫
モンテッソーリ教具は本格的なものだと高価だったり、日本では手に入りづらい場合があります。そのため、100円ショップや無印良品など身近なお店で素材を探したり、牛乳パックや空き箱など身近な物で手作りすることも多いです。「シンプルだけど本質的な体験」ができるよう、お米や小豆、折り紙など和の素材も積極的に取り入れています。日本ならではの四季や行事(ひな祭りや端午の節句)に合わせて活動内容を変えることで、家庭ならではのオリジナリティも出せました。
家族や周囲への理解づくり
祖父母世代からは「そんなことさせて大丈夫?」と言われることもしばしば。でも、子どもの成長や自立した姿を見てもらいながら少しずつ理解を広げてきました。子育て仲間とも意見交換しながら、日本だからこそできる柔軟なモンテッソーリの形を模索しています。
6. これからモンテッソーリを始めたいご家庭へのアドバイス
おうちモンテッソーリは「完璧」を目指さないでOK
モンテッソーリ教育と聞くと、特別な教材や環境が必要だと思いがちですが、実際には日常生活の中で無理なく始めることができます。私自身も最初は「ちゃんとしなきゃ」と思い込んでいましたが、気負わずに子どもの興味を大切にすることからスタートして良かったと感じています。
初心者が気軽に始めるためのポイント
1. 家にあるもので十分
高価なおもちゃや教材を買い揃えるより、身近なもの――例えばスプーンや小さなコップ、お米など――を使って「自分でできる」体験を積ませてあげましょう。
2. 子どもの「やりたい!」を尊重する
親が主導するのではなく、子どもの意思や好奇心を観察して、「自分でしたい」「やってみたい」という気持ちを見守る姿勢が大切です。失敗しても責めず、挑戦する姿そのものを認めてあげてください。
3. 生活リズムに取り入れる
忙しい毎日の中でも、朝食の準備やお片付けなど、普段の生活の流れに自然に組み込むことで続けやすくなります。「今日は特別なことをしなきゃ」と構えず、日常の中で小さなチャレンジを一緒に楽しみましょう。
続けるコツと親としての心構え
親も一緒に成長する気持ちで
子どもだけでなく、親自身も試行錯誤しながら学んでいくという気持ちが大切です。私も「うまくいかない日」が何度もありました。でも、その経験こそが親子の成長につながりました。
焦らず少しずつ
最初から結果を求めたり、「他の子と比べてしまう」ことは避けましょう。子どものペースを信じて、小さな進歩を喜び合う時間を大切にしてください。
まとめ
日本の暮らしや文化の中でも、おうちモンテッソーリは決して難しくありません。「まずはできることから」「子どもの目線で考えてみる」この二つを意識して、家族みんなでゆっくり楽しみながら取り組んでみてください。

